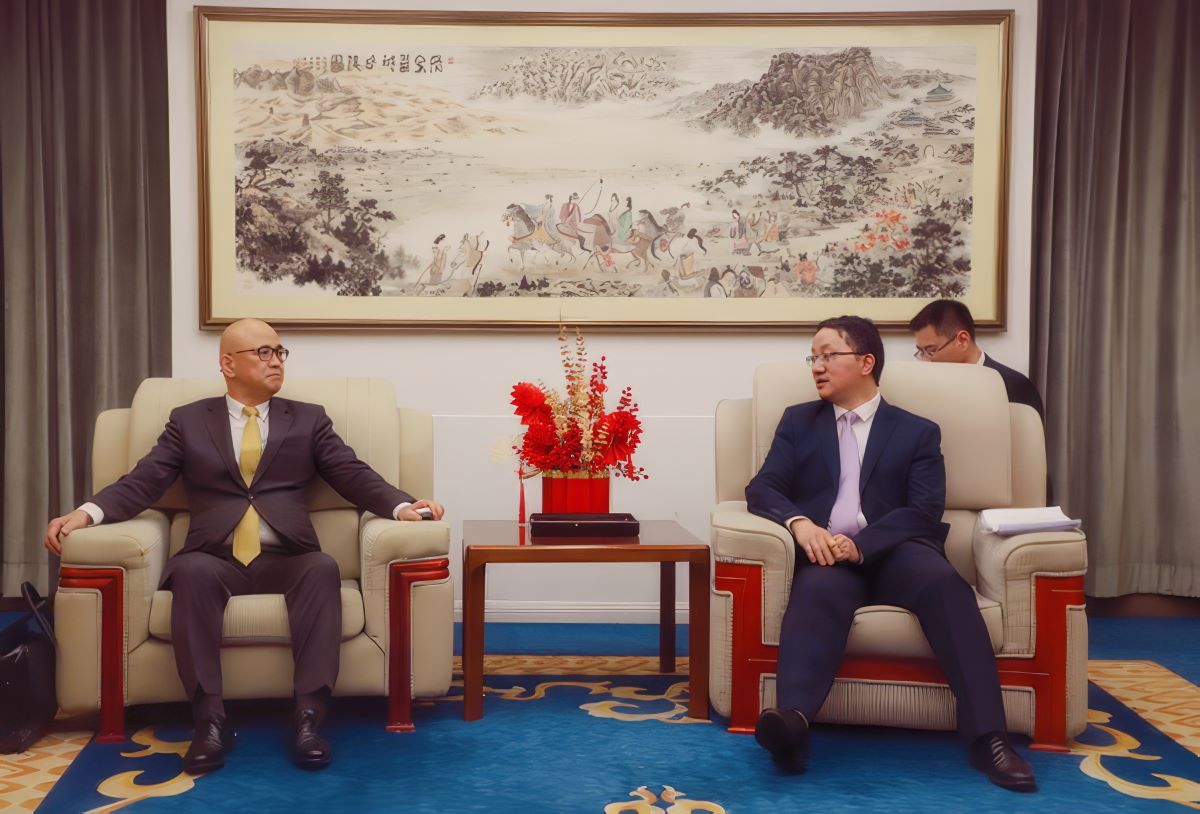伊藤忠(中国)集団の首席顧問を務め、中国日本商会会長として長年にわたり在中日系企業を率いてきた池添洋一氏は、日本の対中経済認識に対して一貫して厳しい。「日本は45年間、中国市場を見誤ってきた」。その言葉は、机上の分析ではなく、現場に身を置き続けてきた経験に裏打ちされた実感である。
中国の工業力と市場構造の変化、日本企業が直面してきた構造的課題、そして日中経済関係を持続的なものとしていくために不可欠な条件とは何か。現場を知る当事者の言葉から、日中経済の現在地が浮かび上がる。
止まらなかった中国
立ち止まった日本
―― 中国で長年ビジネスの最前線に立ってこられたご経験を踏まえ、現在の日中経済関係の「温度感」をどのように捉えておられますか。
池添 日本にいて感じる中国観と、中国にいて実際に肌で感じる現実に、本質的な違いはありません。これは、私が長年中国で仕事をしてきた中で一貫して感じてきたことです。
よく「現地は前向きだが、日本の本社が冷えている」と言われますが、私はこの見方は問題の本質を捉えていないと思っています。現地と本社の間に温度差があること自体は事実ですが、それは結果であって、原因ではありません。
原因は、日本企業の中国に対する基本的な見方が、この45年間ほとんど変わっていないことにあります。日本企業は一貫して、中国を「本質的にリスクを伴う存在」「常に警戒すべき市場」として捉えてきました。その前提が変わらない以上、何か起きるたびに反応は同じになります。
私は過去の大きな緊張局面の時代にも中国の現場にいました。そのたびに日本では、「中国はもう終わった」「撤退すべきだ」という議論が繰り返されました。しかし、現地で見ている限り、中国市場が本当に止まったと感じたことは一度もありません。政治的な緊張や制度変更はありましたが、それによって市場全体が長期にわたり縮小したり、経済活動そのものが停滞したことはありませんでした。
むしろ、中国市場は一貫して拡大を続けてきました。消費も投資も、形を変えながら前に進んできた。その中で起きたのは、中国が止まったという現象ではなく、日本企業の側が「危ない」「やりにくい」と判断し、自ら距離を置いてきたという事実です。
つまり、日中経済関係の「温度感」を下げてきた最大の要因は、中国側の変化ではありません。日本側の心理であり、判断の積み重ねです。私は特別に楽観的な見方をしているわけではありません。ただ、長年現場にいて、現実を見てきた経験から言えば、日本で語られている中国像と、現地で動いている中国経済との間に、決定的なズレがあるとは感じていません。仮にズレがあるとすれば、それは事実そのものではなく、受け止め方の側にあります。
中国は生産拠点ではなく
世界で最も厳しい市場
―― 10年前、あるいは5年前と比べた場合、日中経済関係で最も大きく変化した点は何でしょうか。
池添 最も大きな変化は、中国の工業力と市場構造が、日本を明確に追い越したという現実です。これは印象論ではなく、製造業や投資の現場を見ていれば否定しようのない事実です。にもかかわらず、日本側の認識がその変化に追いついていない。ここに、現在の日中経済関係の大きな歪みがあります。
かつては、日本が技術を持ち、中国がそれを追いかける立場でした。日本企業が設計し品質を決め、中国が大量生産する――そうした役割分担が長く続いてきました。しかし今は、多くの分野で構図が逆転しています。中国企業のほうが意思決定も投資判断も早く、市場の変化への反応も速い。製品開発から量産、市場投入までのスピードで、日本企業が優位にあるとは言えません。
それでも日本企業はいまだに「技術を取られるのが怖い」「競争に巻き込まれるのが不安だ」と言い続けています。しかしこの10年で、中国はもはや「安い生産拠点」ではなくなりました。価格、品質、供給能力、スピードといった点で、企業の総合力が厳しく問われる市場へと変化しています。
中国市場は、もはや数ある選択肢の一つではありません。ここで通用するかどうかが、その企業が世界市場で競争力を持てるかどうかを見極める重要な基準になっています。この構造変化こそが、10年前、5年前と比べて最も大きく変わった点だと考えています。
最大のリスクは、中国を
分からないまま恐れること
―― 日本企業が中国で事業を展開する上での最大のリスクは何でしょうか。また、それを上回る魅力はどこにありますか。
池添 日本企業が中国で事業を行ううえでの最大のリスクは、中国そのものではありません。中国を正しく理解しないまま、曖昧な不安やイメージで意思決定をしてしまうことです。「中国は怖い」という言葉はよく聞きますが、その「怖さ」が何を指しているのかを具体的に説明できる人は多くありません。政策なのか、技術流出なのか、政治的対立なのか。それらが整理されないまま、「危ない」「やりにくい」という感覚だけが先行している。私は、この状態こそが最大のリスクだと思っています。
不安が言語化されないまま意思決定が行われると、判断は過剰に保守的になり、結果として機会を逃し、競争から自ら降りてしまう。よく「中国では契約が守られない」と言われますが、私が長年現場で見てきた限り、民間企業同士の契約が政府によって一方的に覆される例は極めてまれです。「契約リスク」が中国固有の問題だとは言えません。
一方で、中国市場の魅力は、価格や品質、供給能力、スピードなど、企業の総合力が同時に問われる点にあります。ここで鍛えられた企業だけが、グローバル市場でも競争力を持ち続けています。
つまり、中国市場の価値は「成長しているから」ではありません。最も厳しい競争環境であり、そこで勝てるかどうかが企業の実力を決める点にあります。中国を避けることは、リスク回避のように見えて、実は競争から降りる選択になっている。私は、そこにこそ日本企業が見落としている本当のリスクがあると考えています。
本社と現場をつなぎ
企業間の連携を深める
―― 中国日本商会会長として、多くの在中日系企業の声を聞かれてきました。最も多かった課題は何でしょうか。
池添 最も多く聞いたのは、「日本の本社が理解してくれない」という声でした。これは一部の企業に限った話ではなく、多くの在中日系企業に共通する悩みです。現地では、顧客もいて売上も立ち、事業は一定程度うまく回っている。それにもかかわらず、日本で対中関係をめぐるニュースや発言が出ると、本社の空気が一変し、これまで認められていた投資や事業判断が急に止まる。
現場から見れば、なぜ今ブレーキがかかるのか、合理的な説明がないことも多い。市場は動いているのに、自分たちは動けない。競合は前に進んでいるのに、判断は先送りされる。こうした状況が続けば、現地の責任者やスタッフは疲弊し、士気も下がっていきます。この構図は短期的なものではなく、政治的な緊張が高まるたびに、長年繰り返されてきました。
もう一つの課題は、日本企業同士が中国市場で十分に協調できていない点です。個々の企業は努力しているものの、業界として中国政府や地方政府とどう向き合うか、共通の戦略を持てていない。欧米の商会が業界単位で政策対話を行っているのに対し、日本は企業間競争が前に出て、業界としての声が弱くなりがちです。
在中日系企業が直面している問題は、個々の現場努力だけでは解決できません。本社と現場の認識のずれ、そして日本企業同士の連携不足。この二つが重なっている点に、構造的な課題があると感じています。
中国を世界市場の一部
として見られるか
―― 今後、日本企業はどの分野で、どのような姿勢で中国市場と向き合うべきでしょうか。
池添 中国市場というと、飲食や小売といった分野が注目されがちですが、本質はそこではありません。日本企業が中国で本当に取り組む意味があるのは、製造業です。この市場で通用する製品や技術を持てるかどうかが、企業の実力そのものを決める時代になっています。
その点で、ダイキンの姿勢は象徴的です。ダイキンは中国を「コストの安い場所」としてではなく、米欧と同じ世界市場の一部として位置づけ、同じ基準で事業を展開しました。その結果、中国市場でもブランドを確立し、事業をグローバル成長の柱に育てています。
TDKの例も同様です。カセットテープ事業が行き詰まったとき、TDKは中国・深圳で小型電池事業に取り組みました。それがATLです。当時は不安もありましたが、結果としてATLは成長し、今やTDKの利益を支える存在になっています。
重要なのは、「中国で何をやるか」ではなく、「中国をどう位置づけるか」です。世界市場の一部として向き合った企業は、大きな成果を上げています。一方で、そうした判断を取らなかった企業もありました。技術提供や資本参加といった選択肢が存在しながら、最終的に踏み切れなかった。その判断の差が、後の結果として表れています。
これらの事例が示しているのは、中国市場で成功するかどうかは、中国が特別だからではないということです。中国を世界市場の一部として捉えられるかどうか、その判断の違いが、結果の差を生んでいるのです。
外交部アジア局の劉勁松司長と会談
感情と経済を切り分け
対話を続ける
―― 国際環境の不確実性が高まる中にあっても、民間レベルでの経済交流や人的往来は、依然として重要な役割を果たしています。今後、日中経済関係をより持続的なものとしていくために、特に重視すべき点は何だとお考えでしょうか。
池添 私が最も重要だと考えているのは、まず感情と経済を切り分けることです。好き嫌いや政治的な評価があるのは自然なことですが、経済活動まで感情で判断してしまうと、現実が見えなくなります。国際環境が不安定になると、「今は関わるべきではない」「距離を取ったほうが安全だ」という空気が生まれやすくなりますが、経済はそうした空気とは別の論理で動いています。現場では、市場は動き、人は働き、企業同士の関係も続いている。その現実を冷静に見て判断することが欠かせません。
もう一つ重要なのは、直接対話できる人材の存在です。地方政府の担当者や企業トップ、現場の責任者と、通訳や書面を介するだけでなく、自分の言葉で話ができる人間がどれだけいるか。誤解は、対話をしなければ解けません。相手が何を考え、何を重視しているのかは、現場で直接話してみなければ分からない。
私は特別なことをしてきたわけではありません。ただ現場に入り、相手と話し、現実を見てきただけです。それだけで多くの誤解は解けていきました。日中経済関係を持続的なものにするうえで、本当のリスクは中国そのものではありません。中国を「分からないまま避ける」こと、そして考えることをやめてしまうことです。民間レベルの経済交流や人的往来は、政治状況がどうであれ現実をつなぎとめる力を持っています。感情に流されず、現場を見て、対話を続ける。その積み重ねこそが、日中経済関係を支える基盤になると考えています。
取材後記
取材は約2時間に及んだ。昨年来、日中関係が冷え込む中にあっても、池添洋一氏は中国語を交えながら、具体例を示しつつ終始淀みなく精力的に語り続けた。その語りは感情に流されることなく、現場で積み重ねてきた経験と事実に裏打ちされたものだった。
中国市場をめぐる議論が政治や空気論に傾きがちな中で、氏の発言は一貫して「現実をどう見るか」「企業として何を判断すべきか」に軸足を置いている。中国を特別視するのでも、過度に楽観するのでもなく、世界市場の一部として冷静に捉える姿勢は、当事者ならではの重みを持つ。
日中経済関係の捉え方に迷いが生じている今、本インタビューは、日本企業が足元を見直し、今後の判断を考えるための手がかりとなるだろう。
トップニュース
 |
2026/1/30 |
|
 |
2025/12/25 |
|
 |
2025/12/22 |
|
 |
2025/7/25 |
|
 |
2025/6/23 |
|
 |
2025/6/22 |